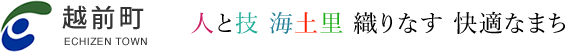令和7年度高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種のお知らせ
高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種は、重症化予防を目的に65歳以上の高齢者等を対象とした定期接種(一部自己負担あり)です。
なお、対象者以外の人や、実施期間以外で接種する場合は、任意接種(全額自己負担)となります。
対象者
町内に住所を有する人で次の1または2に該当する人
1 .昭和36年1月31日までに生まれた65歳以上の人
1に該当する人には、9月下旬に予診票兼接種券を封書で郵送します。
2 .60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓もしくは呼吸機能の障がい、または免疫の機能障がいのため、障害者手帳1級の認定を受けている人
2に該当する人で接種を希望する人は、健康保険課に申請してください。
※接種券を紛失した場合は、健康保険課またはお近くのコミュニティセンターで再発行が可能です。
接種期間
令和7年10月1日から令和8年1月31日まで (医療機関の休診日を除く)
助成回数
実施期間中に各1回
接種費用
インフルエンザ 2,000円(自己負担分)
新型コロナウイルス感染症 7,500円(自己負担分)
持ち物
予診票兼接種券、本人確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)、接種費用
接種場所
R7指定医療機関一覧は 指定医療機関一覧(PDF形式 267キロバイト)
指定医療機関一覧(PDF形式 267キロバイト)
(補足)転出された場合は、越前町の接種券は利用できません。新しい住所地でお問い合わせください。
指定医療機関以外で接種する場合
指定医療機関以外で接種する場合は、一旦接種費用を全額お支払いいただき、後日「高齢者等予防接種費用請求書」(様式ダウンロード)を記入し、下記書類とともに、健康保険課へ提出してください。
必要書類等:予防接種費用の領収書、予防接種済証、助成費の振込み先のわかるもの、印鑑
助成額:
インフルエンザ
接種費用から2,000円引いた額(上限額2,220円)
新型コロナウイルス感染症
接種費用から7,500円引いた額(上限額7,800円)
申請期限:令和8年3月31日まで
新型コロナウイルス感染症予防接種で使用するワクチンについて
定期接種で使用できるワクチンは以下のとおりです。
医療機関によって接種できるワクチンが異なる場合がありますので、どのワクチンを使用するかは医療機関にお問い合わせください。
|
メーカー |
ワクチンの種類 |
|---|---|
| ファイザー社 | mRNAワクチン |
| モデルナ社 | mRNAワクチン |
| 第一三共社 | mRNAワクチン |
| Meiji Seikaファルマ社 | mRNAワクチン(レプリコンワクチン) |
| 武田薬品社 | 組換えタンパクワクチン |
各社のワクチンについて、以下のような副反応が報告されています。また、頻度は不明ですが、重大な副反応として、mRNAワクチンについては、ショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎が知られており、組換えタンパクワクチンについては、ショック、アナフィラキシーが知られています。
| 発現割合 | 50%以上 | 10%以上50%未満 | 1%以上10%未満 |
|---|---|---|---|
| ファイザー社 | 痛み※1、疲労、頭痛 | 筋肉痛、悪寒、関節痛、発熱、下痢、腫れ※1 | 赤み※1、リンパ節の腫れや痛み、嘔吐、疼痛 |
| モデルナ社 | 痛み※1、疲労、頭痛 | 筋肉痛、悪寒、関節痛、吐き気・嘔吐、リンパ節の腫れや痛み、発熱、腫れ※1、しこり※1、赤み※1 | 痛み※2、腫れ※2、赤み等※2 |
| 第一三共社 | 痛み※1、倦怠感 | 熱感※1、腫れ※1、赤み※1、かゆみ※1、しこり※1、頭痛、発熱、筋肉痛 | 赤み※2、腫れ※2、かゆみ※2、熱感※2、しこり※2、痛み※2、リンパ節の腫れや痛み、発疹、腋の痛み |
| Meiji Seikaファルマ社 | 痛み※1 | 倦怠感、頭痛、悪寒、筋肉痛、関節痛、発熱、めまい、腫れ※1、しこり※1、赤み※1 | かゆみ※1、下痢、吐き気、嘔吐 |
| 武田薬品社 | 痛み※1、疲労、筋肉痛、頭痛 | 倦怠感、関節痛、吐き気・嘔吐 | 腫れ※1、しこり※1、赤み※1、発熱、四肢痛 |
各社の添付文書より厚労省において作成したものを参照
※1 ワクチンを接種した部位の症状
※2 接種後7日以降のワクチンを接種した部位の症状
新型コロナワクチン定期接種について(厚生労働省ホームページ)(外部ページ)(新しいウィンドウで表示します)
他の予防接種との関係について
インフルエンザワクチン・コロナウイルスワクチンと他の予防接種(肺炎球菌ワクチン等)との同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。ご希望の方は、医師にご相談ください。
予防接種健康被害救済制度
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、無くすことはできないことから、救済制度が設けられています。接種日や定期接種か否かによって対象となる救済制度が異なります。
対象となる救済制度
| 令和6年3月31日までの特例臨時接種 | 予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種・臨時接種として市町村に請求 |
| 令和6年4月以降の定期接種 | 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求 |
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部ページ)(新しいウィンドウで表示します)
|
令和6年以降の任意接種 |
医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求 |
医薬品副作用被害救済制度について((独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ)(外部ページ)(新しいウィンドウで表示します)
関連リンク
- インフルエンザワクチン・新型コロナワクチン接種を迷っているあなたへ((一社)日本ワクチン産業協会ホームページ)(外部ページ)(新しいウィンドウで表示します)
※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 健康保険課
-
電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235
アンケートにご協力下さい
この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。