【税の質問箱】個人住民税(町・県民税)について教えてください
目次
問1. 私の夫は今年の2月に亡くなりました。昨年の所得に対する住民税はかかるのでしょうか。
問2. 私は昨年の12月に越前町から町外へ引っ越しました。今年の住民税はどこに納めますか。
問3. 昨年度よりも町・県民税が上がったのはなぜですか。
問4. 昨年収入がなかったのですが、申告する必要がありますか。
問5. 家族の税法上の扶養に入っているのに、納税通知書が届いたのはなぜですか。
問6. 給与から住民税が天引きされているのに、納付書が届いたのはなぜですか。
問7. 同じぐらいの年金なのに、夫は住民税がかからず、私には住民税がかかっているのはなぜですか。
問8. 年金から住民税が天引きされているのを止めてほしいのですが。
問1. 私の夫は今年の2月に亡くなりました。昨年の所得に対する住民税はかかるのでしょうか。
町・県民税は1月1日現在にお住まいの市区町村で、前年中(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。そのため、1月2日以降にお亡くなりになった人には、その年度の町・県民税が課税されます。納税義務は相続人に承継されますので、お亡くなりになった人の町・県民税は相続人に納めていただくことになります。
問2. 私は昨年の12月に越前町から町外へ引っ越しました。今年度の住民税はどこに納めますか。
町・県民税は1月1日現在にお住まいの市区町村で、前年中(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。そのため、今年の1月1日現在にお住まいの市区町村へ納めることになります。また、今年の1月1日に越前町にお住まいの人は、1月2日以降に町外へ転出された場合でも、当該年度分の町・県民税は越前町に納めていただきます。転出先の市区町村では課税されません。
問3. 昨年度よりも町・県民税が上がったのはなぜですか。
次の理由に該当する場合がほとんどです。
- 前年中の所得が、前々年中の所得よりも増えていることが考えられます。昨年度の納税通知書と併せて所得額等をご確認ください。
- 配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除等の所得控除を申告していないことが考えられます。源泉徴収票や確定申告書の控えをご確認ください。
- 扶養に入れた親族の合計所得額が48万円を超えている場合、扶養控除を受けることができません。扶養に入れた親族の所得については、本人にご確認ください。
問4. 昨年収入がなかったのですが、申告する必要がありますか。
今年の1月1日現在、越前町にお住まいの人は、前年中に収入がない人でも次に該当する場合は申告が必要です。
- 収入がなかった人で、税法上の扶養となっていない人
- 失業保険、遺族年金や障害年金など非課税年金の給付を受けていた人
- 病気療養中であった人
- 学生 など
町・県民税や国民健康保険税、介護保険料、保育料等の算定の基礎となるほか、児童手当や所得証明書等の交付に必要な手続きですので、早めに申告してください。
問5. 家族の税法上の扶養に入っているのに、納税通知書が届いたのはなぜですか。
税法上の扶養に入ることができる基準と、町・県民税の非課税基準が異なるため、町・県民税が課税される場合があります。町・県民税の非課税基準については、次の「非課税となる人(均等割も所得割もかからない人)」をご確認ください。
町・県民税が非課税となる所得の条件は、次のとおりです。なお、税法上の扶養になっている場合でも、次の条件に該当しない場合は課税されます。
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年の合計所得金額が、次の計算式に当てはめた金額以下の人
【計算式】28万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+16.8万円
※同一生計配偶者および扶養親族がない場合は38万円
問6. 給与から住民税が天引きされているのに、納付書が届いたのはなぜですか。
次のような場合は、給与から住民税が天引きされていても、納付書等で自分で納付していただくことがあります。
- 給与・公的年金等に係る所得以外(本年度の4月1日において65歳未満の人は給与所得以外)の所得に対する住民税については、確定申告や住民税申告により、徴収方法を選択することができます。住民税を給与から差し引かずに、納付書等で自分で納付することを希望(「自分で納付」欄に〇を記入)した場合
- 給与以外の所得があり、給与以外の所得に対する住民税額が大きく、給与から引き切れない場合
- 過年分をさかのぼって申告したことにより、過年度分の住民税が増額となった場合
問7. 同じぐらいの年金なのに、夫は住民税がかからず、私には住民税がかかっているのはなぜですか。
同じぐらいの年金収入でも、税法上の扶養親族がいる場合などによって非課税となる金額が変わります。住民税が非課税となる条件については、問5の《非課税となる人(均等割も所得割もかからない人)》をご覧ください。
公的年金等の収入金額は、年齢により所得金額(公的年金等の雑所得の金額)に直す計算方法が異なります。次の例は、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合です。
- 65歳未満の人・・・年金収入が60万円までは、年金所得は0円
- 65歳以上の人・・・年金収入が110万円までは、年金所得は0円
そのため、年金収入が110万円の場合、65才以上の人は年金所得は0円ですが、65歳未満の人は年金所得が50万円となり住民税が課税される可能性があります。
問8. 年金から住民税が天引きされているのを止めてほしいのですが。
本年度の4月1日現在、65歳以上の人で公的年金等の所得に対して町・県民税が課税される場合、公的年金から特別徴収(年金天引き)により町・県民税を納付することになります。この制度は、地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。町・県民税の納付方法が変わるだけで、年間の税負担が変わることはありません。
次の要件すべてに該当する人は、特別徴収の対象になります。
- 年額18万円以上の公的年金(老齢基礎年金等)を受給している人
- 介護保険料が年金から特別徴収されている人
- 特別徴収の対象となる町・県民税が、支給される老齢基礎年金等の額(所得税、介護保険料、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を控除した後の額)を超えない人
関連リンク
関連ファイル
※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 税務課
-
電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235
アンケートにご協力下さい
この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。
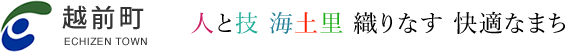
 納税の方法(PDF形式 339キロバイト)
納税の方法(PDF形式 339キロバイト)