自主防災組織で「災害に強いまち」をつくりましょう
自主防災組織とは
自主防災組織とは、地域住民が連携・協力して災害から「自分たちの命・地域を自分たちで守る」ために活動することを目的に結成する組織のことをいいます。日頃から災害に備え、防災に関する意識啓発や訓練など様々な活動を行い、災害が発生したときに地域住民が連携・協力して地域の被害を最小限に抑えることが自主防災組織の役割です。
防災・減災の要となる「共助」
災害が起きたときに必要な助けや支援には、自分の身は自分で守る「自助」、役場や消防・警察等が行う「公助」、そして、自分たちの住んでいる地域は自分たちで守る「共助」の3つがあります。その中でも住民自身が協力して自分たちの身を守る「共助」は、防災の要といえます。そのために自主防災組織の役割が大切になります。
自主防災組織をつくりましょう
阪神・淡路大震災では、生き埋めや建物などに閉じ込められた人々のうち、消防などの公的機関(公助)による救出はわずか2%で、多くは自力(自助)または家族や隣人などの地域住民(共助)によって救助されています。地域住民が連携・協力し、救助や消火にあたることが被害を最小限にすることにつながります。
災害が発生した時、自分の命、地域住民の命・財産を守れるのは、自分自身とそこに住む地域住民です。自分と自分のまちを守るために自主防災組織を結成し、「災害に強いまち」をつくりましょう。
自主防災組織の設立に関する届出について
自主防災組織を設立する場合は、下記の様式にご記入の上、防災安全課までご提出ください。
組織名称などを変更される場合は、下記の様式をご提出ください。
自主防災組織の役割
地域内で防災活動を行う自主防災組織には、次のような役割があります。
いざというときのために、平常時から地域で連携・協力をしながら防災活動に取り組むことが大切です。
平常時の活動
防災知識の普及啓発
勉強会(講習会)の開催など
地域の安全確認
地域内の危険個所の把握と防災マップの作成など
防災訓練の実施
初期消火訓練、情報伝達訓練、避難訓練など
防災資機材の点検整備
防災資機材(ヘルメット、担架、リヤカー、バケツなど)の管理
災害時の活動
情報の収集伝達
地域内の被害情報などの収集や防災機関への伝達、役場や消防署などからの情報の周知
初期消火
消火器やバケツリレーなどによる初期消火活動
避難誘導
住民の安否確認、避難誘導など
救出救護
簡単な工具・防災資機材を使用した救出、負傷者の救護など
給食給水
食料・飲料水の調達、炊き出しなど
自主防災組織補助金
自主防災活動の促進を図るため、自主防災組織が活動上必要な防災資機材等の購入に対して補助金を交付しています。(詳細はこちらから)
関連ファイル
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 防災安全課
-
電話番号:0778-34-8721
ファックス番号:0778-34-1236
アンケートにご協力下さい
この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。
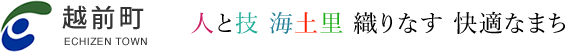
 自主防災組織設立届(リッチテキスト形式 51キロバイト)
自主防災組織設立届(リッチテキスト形式 51キロバイト) 防災会規約(ワード形式 33キロバイト)
防災会規約(ワード形式 33キロバイト) 自主防組織図等(エクセル形式 53キロバイト)
自主防組織図等(エクセル形式 53キロバイト)